2025.04.19
給料あり vs 無給インターン、どっちを選ぶべきか?
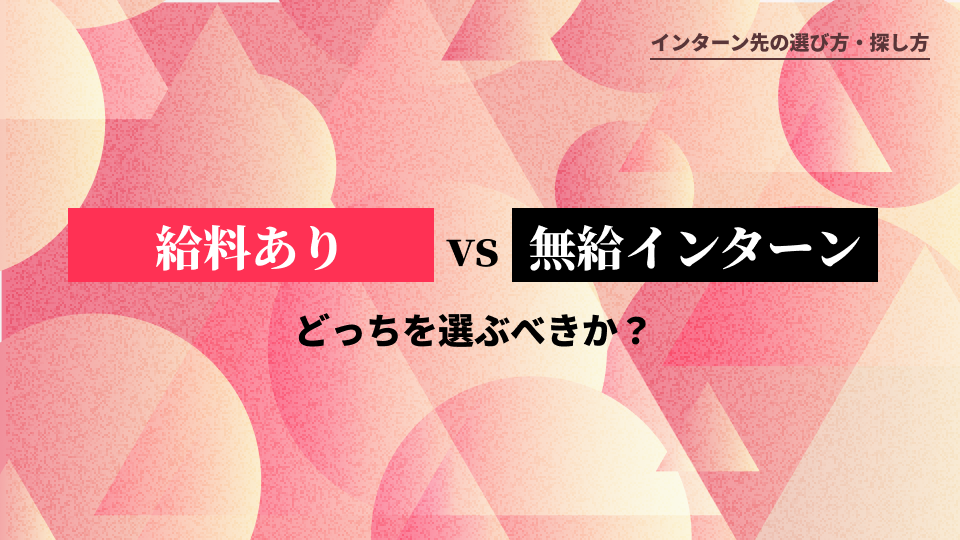
はじめに
長期インターンを探す際、多くの学生が「有給か無給か」で悩みます。特に営業職のインターンでは、成果報酬型の企業も多く、報酬制度が複雑なケースもあります。
本記事では、有給インターンと無給インターンの違いや、それぞれのメリット・デメリットを定量データを交えて解説し、どちらを選ぶべきかを考察します。
1. 有給インターンと無給インターンの違い
(1) 定義と特徴
| 項目 | 有給インターン | 無給インターン |
| 報酬 | 時給・成果報酬あり | 無報酬または交通費支給のみ |
| 業務内容 | 実務的な業務が多い | 研修やアシスタント業務が中心 |
| 企業の期待度 | 成果を求められる | 学習の機会が重視される |
| 学べるスキル | 即戦力としての実務スキル | 基礎的な業務知識 |
| 選考難易度 | 高め(経験やスキルを重視) | 比較的低め(未経験歓迎) |
企業によっては「無給でも経験価値が高い」場合もありますが、基本的に有給インターンのほうが実践的な業務を経験しやすい傾向にあります。
2. 有給インターンのメリット・デメリット
(1) メリット
- 経済的な負担が軽減できる
- 時給相場(東京都):営業職1,500円〜2,500円、マーケティング職1,300円〜2,000円
- 週3回、1日5時間勤務で約9万円〜15万円の収入
- 実務経験を積める
- 営業職なら商談・テレアポ、マーケティング職なら広告運用・SNS運営など、実践スキルを学べる
- 就活で有利になる
- 「〇〇の業務で成果を出した」と具体的なアピールが可能
- 長期インターン経験者の70%が「就活で役立った」と回答(2023年調査)
(2) デメリット
- 成果が求められる
- 結果を出せないとインセンティブが得られない
- プレッシャーを感じることがある
- 業務の難易度が高い場合がある
- ベンチャー企業では「インターン=即戦力」として扱われることが多い
- 研修が少ない企業だと、未経験者は苦労することも
3. 無給インターンのメリット・デメリット
(1) メリット
- 未経験者でも参加しやすい
- 研修・OJTが充実している企業が多い
- スキルゼロから学べるため、初心者に適している
- 大手企業や外資系のインターンに参加できるチャンスがある
- 有名企業の短期インターンは無給のケースが多い
- 「○○社でインターンをした」と履歴書に書ける
- プレッシャーが少なく、学びに集中できる
- 成果を求められるプレッシャーが少ないため、気軽に挑戦しやすい
(2) デメリット
- 金銭的な負担が大きい
- 交通費のみ支給の企業もあり、生活費の補填ができない
- アルバイトとの両立が難しい
- 実務経験が少ないことがある
- 企業によっては雑務や見学が中心
- 「本当に成長できるのか?」を事前に見極める必要がある
- 就活に直結しない場合も
- 実績が残らず、就活で具体的なエピソードとして話しにくい
4. どちらを選ぶべきか?
| 目的 | 有給インターンが向いている人 | 無給インターンが向いている人 |
| 経済的な安定 | 生活費を稼ぎたい | 金銭的に余裕がある |
| キャリア形成 | 実務経験を積みたい | 基礎知識を学びたい |
| 難易度 | 結果を出すことにやりがいを感じる | 学習を優先したい |
| 企業の規模 | ベンチャー・スタートアップ向け | 大手・外資系向け |
結論:目的に応じて選択することが重要
- 即戦力スキルを身につけ、就活やキャリアアップにつなげたいなら有給インターン
- 未経験から学び、業界の雰囲気を知りたいなら無給インターン
5. 企業選びのチェックポイント
インターンの質を見極めるために、以下の点を確認しましょう。
(1) 業務内容の具体性
- 「営業のサポート」など曖昧な表現の企業は要注意
- 実際に何をするのか、面接時に確認
(2) フィードバック体制
- 成果を出すための研修や定期的な評価制度があるか
- 先輩社員やメンターがつくかどうか
(3) 企業の評判
- SNSや口コミサイトで過去のインターン生の評価を確認
- 「ブラックインターン」にならないよう、労働環境を調査
6. まとめ
インターンを選ぶ際、有給か無給かは大きなポイントですが、自分の目的に合った選択をすることが最も重要です。
✅ 収入を得ながら実務経験を積みたいなら有給インターン
✅ 未経験から学びたい、業界研究をしたいなら無給インターン
また、どちらを選ぶ場合でも、「業務内容」「成長環境」「フィードバック体制」をしっかりと確認し、成長できる企業を選びましょう。